第002話
第三章 敗北感とそれから
辛い気分にはなったけど、それでも、僕達は楽しかった思い出は残っている。
その思いがあれば、僕らは人間の為に戦える。
旅支度をすませ、僕はシャーロットと共に、エヴァーロード家の屋敷を後にした。
目指すは、リチュオル家の真祖の一人を捜す事だ。
正直、手がかりは無い。
各地に散らばっている情報屋と連絡を取っていって、真祖を探し出すしかない。
真祖達は世界中にバラバラに潜んでいる。
だから、どこでどの真祖とあたるかわからない。
だけど、人里とは離れた場所に潜んでいるというのは解る。
真祖は姿を隠すには力が大きすぎるからだ。
都会にいたらすぐに解る。
だからエサである人間の調達は眷属の怪物達に任せて、自分達はどこかの僻地に潜んでいるんだ。
そのため、世界中を旅すると言っても、都会の有名な観光スポットはまずないと言って良い。。
全く無名の観光名所とはほど遠い場所を探す事になる。
旅行気分で行くのなら、それはそれでがっかりするだろうけど――
僕らは戦いに行くんだ。
そんなのは関係ない。
とは口で言ったものの――
現在は、アメリカのアリゾナ州の北部にある峡谷……つまり、グランドキャニオンらへんにいる事はわかるんだけど、観光スポットの場所からはかなり外れた場所をうろついている。
グランドキャニオンならもっと良い場所とかありそうだ。
正直、あんまり、良い眺めの所じゃない。
僕らは、ここに真祖の一人がいるって聞いてやってきた。
現在、居所がつかめているのはここしかないため、必然的にこの場所を選択する事になったんだ。
ここに居るのはベネディクトという名前の真祖だ。
力は全くの未知数。
どんな奴かも解らない。
だけど、戦うしかない。
僕らはその為に修行したんだ。
だけど、想定外の状況だった。
その場には他に二名の真祖もいた。
「あぁ、キャサリン、君にはこのベネディクトがふさわしい」
「いや、キャサリン、このデイヴィッドこそふさわしい」
「どうしようかしらね〜」
どうやら、キャサリンという女真祖をベネディクトとデイヴィッドという真祖が取り合っているらしい。
これは予想外だった。
一人でも大変なのに三人の真祖を相手に勝てる筈もない。
「くそっ、予定外だ……まさか三人もいるとは……」
「シャーロット引き返そう。今はとても無理だ」
「そ、そうだな」
僕とシャーロットがその場を離れる相談をしていた時――
「ねぇ、貴方達、私にふさわしいのはどっちだと思う?」
キャサリンが目の前にフッと現れた。
かなりの距離を取っていたのに、いつの間に?
僕達は咄嗟に身構えた。
だけど、はっきりと解る。
今のままでは一瞬で殺される。
全然、勝てる気がしない。
持っている器が違いすぎる。
それ程の威圧感だった。
だけど、泣き言なんて言っていられない。
僕達は持てる力を総結集させてキャサリンに襲いかかった。
だけど、僕らの【錬想】が全く通じなかった。
キャサリンはまるで何事もないようにひらりとかわしていく。
他の二人の真祖達も僕達などまるで眼中にないかの様に、キャサリンの手助けには向かわず、アプローチを繰り返していた。
キャサリンも僕達の攻撃を避けながら、二人の真祖のアプローチをのらりくらりとかわしていた。
力の差は歴然。
というか、全然相手にもされていなかった。
真祖達は、まるでエヴァーロード家との戦いなどどうでも良いとでも言うような態度だ。
そして――
「そうだわ、鬼ごっこをしましょう。この女の子を捕まえた方とデートしてあげるわ。殺しちゃだめよ。生け捕りにするの。殺しちゃったらバツゲームね」
キャサリンはシャーロットを指してそう言った。
遊んでいる。
完全に遊ばれてしまっている。
遊び相手くらいにしか思われてないんだ。
こっちは決死の決意で来たっていうのに。
向こうはどうでも良い相手としか見ていない。
悔しい。
悔しかった。
本当に悔しかった。
力の差がここまであった事。
相手にもされていない事。
そして、追いかけてくる真祖二人から逃げ回る事しか出来なかった事がだ。
「おいおい、かくれんぼになってしまったなぁ〜どこ行った?」
デイヴィッドがニヤニヤしながらつぶやいた。
「死にたくなかったら出てこいよぉ〜」
ベネディクトも笑いながら叫ぶ。
敵にからかわれている。
悔し涙が止まらない。
僕は囮になるからシャーロットに逃げてと言った。
シャーロットはそんな真似が出来るかと突っぱねた。
そうだ、僕達は生き延びる事に必死だった。
それでも奴らにとっては暇つぶしのお遊びでしかない。
僕らに出来た事――
それは奴らに見つからず逃げ延びる事が出来たって事だ。
奴らから逃げおおせた。
それだけが、プライドを微かに保てた。
だけど、奴らは本気で追いかけて来なかった。
見つからなかったら、それならそれで良いくらいにしか思ってないだろう。
それが解るけど、僕とシャーロットは口に出さなかった。
出したら負けだ。
そう思ったからだ。
いきなり、ボスの所に行った僕らがバカだったのか。
初戦は惨敗というにも及ばない無様な醜態をさらした結果に終わった。
アドルフさんが強く反対したのが今になってよくわかった。
奴らと僕らの力では次元が違いすぎる。
一矢報いるどころか、敵としても認められなかった。
その夜、僕らは身を寄せ合って泣き腫らした。
くやしくて、くやしくて、くやしくて、くやしくて、――たまらない。
震えが止まらない。
怖かった。
相手に思いっきりなめられて、それでもどうすることも出来なかった。
翌日から、僕らは前にも増して修行に打ち込んだ。
泣き腫らした事で、気持ちがスッキリした。
力不足を知った事で、前より明確な目標が出来たからだ。
僕らはからかわれたけど、負けてない。
死んでないからだ。
まだ、やれることはある。
何百年もかかって来たエヴァーロード家の戦いがそんなに簡単に終わるなんて初めから誰も思っちゃいない。
足りない事がたくさんあるって解ったんだ。
これは後退じゃない。
前進だ。
そう思うことで僕らはもっと強くなれる気がした。
今は実力がかけ離れすぎている。
もっとだ。
もっと、もっと、もっと力をつけて、いつか真祖達を――
そう、割り切る事にした。
世界中を回り修行を積んだ。
各地の色んな事を吸収していった。
気付けば、あっという間に一年という月日が経過していた。
様々な怪物達とも戦い、一年前とは全く別人のような成長をしたと思っている。
その間、一皮も二皮もいや、何十皮も剥けた。
もう、当時の僕らじゃない。
今度は無謀とは言わせない。
第四章 眷属
僕らは、一年前逃げ帰ったグランドキャニオンに戻って来ていた。
「うむ、久しぶりだな」
「そうだね、シャーロット」
「こうして見ると、なかなかのものだな。前は景色を見る余裕もなかった。大自然の大きさに対して自分達の小ささを知ったという所だな」
「キャサリン、デイヴィッド、ベネディクト……あの時の屈辱は忘れない。僕らははい上がってきた」
「奴らは今、ここにはいない……居るのは眷属共だ。だが、この一年の成果を試すには丁度良い。私達は慌てない、一歩一歩、奴らに近づいて行けばいい。まずは眷属共からだ。行くぞ、道久」
「了解、シャーロット」
僕らは前に進む。
シャーロットとはこの一年で随分親密になった。
彼女は僕の事を【倉沢】から【道久】というファーストネームに呼び変えて呼ぶようになった。
それだけ、時間が経ったって事だ。
苦楽を共にして、一年前より、お互いの考えが解るようにもなっていた。
個々の力もチームワークも前とは比べものにならない。
だが、奢らない。高ぶらない。
奢り高ぶりは自分を見失わせる。
だから、冷静に自分達を分析する。
何が自分達に足りないのか、何をしていけば良いのか。
それだけを考えて、この一年、過ごして来たんだ。
眷属――リチュオル家の真祖に力を分け与えられた者達。
僕らは中位眷属までは倒した経験がある。
眷属は上から【特別眷属】、【上位眷属】、【中位眷属】、【下位眷属】とある。
真祖が自らの血を分け与えたのは【特別眷属】か【上位眷属】となり、それらを子供と仮定すると孫にあたるのが【中位眷属】や【下位眷属】となる。
【下位眷属】が従来の吸血鬼と同じ様な特徴を持っていて、【下位眷属】に血を吸われた者はグールとなる。
位で言えば更に下の【最下位眷属】となるが、【最下位眷属】は眷属として認められていない。
グールに喰われた者もグールになり、上下関係は基本的になくなるからだ。
【最下位眷属】達は無数の倒し方が存在する。
【下位眷属】も従来の吸血鬼と同じ弱点を持つため、人間でも倒す事は可能だ。
問題は【中位眷属】以上だ。
【中位眷属】以上には従来の吸血鬼の弱点が変更されていたりする。
その為、倒し方も工夫がいる。
例えば、聖水――これもそのままでは利かない。
倒すには一工夫必要となる。
特殊な塩基配列を聖水に組み込む事で初めてダメージを与える事が出来る。
【上位眷属】以上の眷属達の倒し方も基本的には一緒だ。
だけど、比較的、弱点が分かり易い【中位眷属】に比べて、【上位眷属】以上はその倒すべき要素は極めてわかりにくい。
眷属達との戦い――それはウィークポイントを探す戦いでもあるんだ。
上手く、見つける事が出来れば【特別眷属】だって、倒すことは可能だ。
僕はこの一年で、その事をたたき込まれた。
ようやく、もっと高位の眷属達に挑戦する自信がついたから訪れたんだ。
再び、この屈辱の地へ。
このグランドキャニオンには情報では、複数の【上位眷属】がいるって話だ。
真祖ベネディクトの支配地域だから、ここには、ベネディクトの眷属が常駐している。
不真面目な性格をしていたから、大方、領地をほったらかしにして、キャサリンのおしりでも追いかけているんだろう。
一年の修行くらいでは、残念だけど、ベネディクトには勝てる気はしない。
だけど【上位眷属】くらいなら倒せるはずだ。
僕らはその目算がついたからここを訪れたんだ。
「道久、参るぞ」
「オッケー、シャーロット」
僕らは敵地に足を踏み入れた。
まずは、僕が小さな昆虫型のフィギュアを鞄から取り出した。
こいつは何もない普通のフィギュアだ。
だけど、こいつに【錬想】で超小型カメラを植え付ける。
そして、【伝気】によって、虫の様に見せかけて飛ばした。
こいつで偵察をするためだ。
それをシャーロットが【錬想】で作り出した映像転送装置で受信させて様子を窺う事にした。
敵を知り、己を知れば百戦危うからずだ。
まずは、敵の情報を得ることが先決だからだ。
偵察昆虫は順調に敵地の奥へと進み、怪しまれない様に昆虫の動きを模倣させて、あくまでも自然に、僕達に情報を流す。
僕らの目的は眠っている【特別眷属】を倒す事だ。
【特別眷属】――その名称が示す様に、真祖にとっても特別な眷属だ。
【上位眷属】まではいくらでも作れるが、【特別眷属】はそうはいかない。
真祖の力を直接分け与えているため、替えがきかないからだ。
言ってみれば、真祖の分身と言っても良い。
だから、【特別眷属】を倒すという事は真祖の力を削るという事と等しい。
その為、真祖達は【特別眷属】達を僕らがすぐ手の届く場所に配置していない。
僕らの相手は【上位眷属】までに任せておいて、たいがいの【特別眷属】は眠らせている。
だったら、何故、役にも立たない【特別眷属】を作るのか?
それは、いくつか説がある――
一つは真祖は力が大きくなりすぎて、全ての力をその身一つにしまっておくと、自らの身体を傷つける事になるから使わない分を【特別眷属】に分け与えているという説。
一つは人間が服を着るように、真祖も能力を服と同じように考えていて、使わない分は、ハンガーにかけるようにしまっておいているという説。
一つは【特別眷属】だけを本当の子供の様に思っていて、大切な我が子を危険な場所に起きたくないため、眠らせているという説。
等がある。
どれが本当か、わからない。
どれか一つか、全てか、はたまた、別の理由があるのか?
それは解らない。
だけど、真祖が【上位眷属】以下とは別の扱いをしている事から【特別眷属】と僕らから呼ばれている。
力量不足の僕らに今できる事――
それは、真祖の力を削ることだ。
だから、僕達は情報を収集して、なるべく安全に、【特別眷属】を始末していく。
今までは、アルバートさんやクレアちゃんが主にやっていた仕事だ。
これからは、僕らもそれをやっていく。
実は、このベネディクトの【特別眷属】達こそ、エヴァーロード家にとって絶好の獲物でもある。
主であるベネディクトが他の真祖に比べて【特別眷属】に対して無頓着な為、力を削る相手としては最高の獲物となっている。
元々は最も【特別眷属】の数が多い真祖だった。
有名な【レメゲトン】の七二人の悪魔と同じ名前が与えられた七十二体の【特別眷属】を持っていた。
だけど、代々のエヴァーロード家の戦士達が倒して行って、今では残り三分の一にまで数を減らしているらしい。
しかも、倒された三分の二の内、半数は最近、アルバートさんとクレアちゃんが倒していたらしい。
情報によると、三分の一に減ってもベネディクトは相変わらずの無頓着ぶりで、【特別眷属】の保護を各地に配置した【上位眷属】に任せ、キャサリンを追いかけるという生活を続けているらしい。
まだ、三分の一いるから良いと思っているのか、それとも【特別眷属】さえ、どうでも良いと思っているのか。
何にしてもこれはチャンスなんだ。
ベネディクトが油断している内に、力をそぎ落とさせてもらう。
僕らに出来るのはそれだけだ。
ここに居る特別眷属の名前は【シュトリ】だ。
伝説では女性の秘密を暴く力を持ったグリフォンの翼を持つ豹、もしくは美しい人間の悪魔とされているけど、それはあくまでも伝説の中での話だ。
ここで眠っているのは名前こそ同じだけど、中身は別物の【特別眷属】だ。
悪魔じゃない。
恐らく、七二人の悪魔と数が同じだから、適当に、ベネディクトがつけた名前だろう。
現に、この【シュトリ】は豹というより――翼が生えたオオカミの様な姿をしているので、それは同じ七二人の悪魔であるならば【マルコシアス】とつけるべきだろう姿をしている。
ベネディクトは性格的にてきとうな男だというのがその名前の付け方からもよくわかる。
一年前も僕らをギリギリの所まで追い詰めたけど、急にやる気を無くして見つけるのを諦めたし。
アルバートさんとクレアちゃんはこの【特別眷属】の目を醒まさせた上で、力づくで倒している。
だけど、僕らにはそんな力は無い。
あくまでも眠っている内に処分する。
これがベストな作戦だ。
前回の時の様に、想定外の事態が起きないように慎重に辺りを警戒しながら偵察を続けた。
確認出来たのは【シュトリ】を守る【上位眷属】が三体、【中位眷属】か【下位眷属】が二三体だった。
念のために、周りをくまなく探して見たけど、新たに眷属は発見出来なかった。
【上位眷属】は三体か……
初戦だし、一体と戦いたかったけど、【特別眷属】を守っているんだ、三体でも少ない方だ。
ここはGOサインでオッケーだな。
「シャーロット、上位三、中位及び下位が二三だ。僕らなら出来ると思うよ」
「そうだな、いくか」
「オッケー行こう」
「お互いの武運を」
「作戦は……」
僕らは万全の準備をして、ターゲットのいる目的地に忍び寄った。
敵は捕らえてきた人間をエサに食事中だった。
可哀相だけど、攫われて来た人間達は既に絶命している。
助けてもお墓を作ってあげるくらいしか出来ない。
待ってて。
今、こいつらを倒して、お墓、作ってあげるからね。
親元に帰してあげたいけど、僕らにはそれをやっている余裕はない。
せめて、こことは別の安住の地にお墓を作ってあげるのが、精一杯だ。
人間の敵。
【レス】の眷属。
全員、生かして帰さない。
僕らは風を利用して上空に飛び、地上からは見えにくい素材の気球型の物体を作り出し、身をそこに潜めてゆっくりと落下していった。
敵は完全に油断している。
僕らに気付いていない。
最初の一体目のターゲットは【上位眷属】と決めている。
奇襲による一撃で、強い奴を上手く一体倒せればと思っての作戦だ。
僕らは人間の骨をバリバリと食べている熊のような【上位眷属】の頭上二十メートルくらいの位置まで落下した時、気球から飛び出し、挟み撃ちでそいつを仕留めた。
「敵か?」
別の【上位眷属】――テナガザル型の眷属が叫ぶ。
それを合図に僕達は取り囲まれた。
だけど、それも計算の内だ。
あらかじめ、外に仕掛けておいた爆薬を爆発させる。
敵の意識が外にも向けられる。
その隙を僕らは見逃さない。
外の罠と敵の懐に入った僕らとの挟み撃ちで次々と敵を倒していく。
電光石火の早さで、次々と敵をなぎ倒して行って、残すは三メートルのテナガザル型とホワイトタイガーの様な二体の【上位眷属】のみ。
意外と簡単だったな。
そう思った。
後はこの二体を一人一殺で倒せば、残すは無防備な【シュトリ】のみ。
そう高をくくっていた。
が、そんなに甘くなかった。
残った二体の【上位眷属】がまるで風船が破裂するかの様にパンパンと破裂した。
「な、なんだ?」
「一体……」
僕らは軽く驚いた。
何が起きたか解らなかったからだ。
その時――
パチパチパチ……
手を叩く音がした。
見ると、いつの間にか、【シュトリ】の側に四つの影が。
人間?
いや、違う。
この雰囲気は……眷属だ。
「【上位眷属】を倒したと思ったかい?」
「ちょっと考えが甘いんじゃない?」
二つの影が口走る。
その時、初めて理解する。
今まで【上位眷属】と思っていた、三体も所詮、【中位眷属】に過ぎなかった事。
本物の【上位眷属】は目の前にいる四体だという事に。
退避しようと思ったけど、瞬時に囲まれた。
逃げ道をふさがれてしまっている。
今まで戦って来た相手とは格が違う。
強い。
それが、よく解った。
「自己紹介しようか。僕の名前はイースト、左隣からノース、ウエスト、サウスだよ。そう、東西南北だ。困るよね、ちゃらんぽらんな父親だと。その時の気分でつけられる。僕らの名前に意味なんて全然ないんだよね〜」
イーストがニヤニヤ答えた。
親がそうだと子供も似るのかどいつもこいつも適当な性格っぽい顔をしている。
間違いない。
こいつらは、ベネディクトの眷属だ。
実力はこれまで僕らが戦ってきた眷属より、ずっと強い。
見た目は普通の人間と変わらない。
だけど、中身は全くの別物だ。
ここからが戦いの本番だ。
僕らはそう直感した。
第五章 上位眷属との戦い
僕とシャーロットは目で合図した。
経験を積んでいるからアイコンタクトで相手の考えている事は大体わかるようになっていたからだ。
僕らが出した結論は、【シュトリ】が目を醒まさない様に、少しずつ、この場を離れながら、戦うという事だった。
【上位眷属】と言えば、真祖が直接血を与えた直属の眷属だ。
こいつらを倒して、初めて僕らは一人前と言える。
戦闘態勢が万全な僕らに対し、奴らは……
「あぁ〜負けたぁ〜、じゃあ、俺が出るか」
「頑張ってね、サウスちゃん」
「僕らはあっちで見学してるからね」
「ガンバ」
お気楽にもじゃんけんで、僕らの相手を決めていた。
別に僕らは四対二でもやるつもりだったけど、自信過剰なのか、奴らは一人で僕らの相手をするつもりらしい。
確かに、奴らは上位眷属――、今までの眷属達とは実力が違うのだろうけど、なめてもらっては困る。
でも、油断大敵という言葉もある。
僕らはあくまでも慎重かつ的確に倒すだけだ。
奴らが油断している内に、僕らは一体倒させてもらうだけだ。
「ちっ、仕方ねぇ、ほら、相手してやんよ。かかって来いよ、どこぞの馬の骨共」
まるでバツゲームで仕方なく戦うような気持ちで対応しているようなサウス。
だけど、僕らの攻撃は既に始まっている。
僕らが今、構えを取っている姿は【錬想】で作ったコピーだ。
本物の僕らは地中から【ニエンテ】を使って移動していた。
【ニエンテ】――イタリア語で【無】という意味だ。
イタリアで開発された能力で、能力の特徴としては、壁や地中など、通れない場所を通る能力だ。
この力は自分の体細胞をナノレベルで瞬時に置換を繰り返す事によって、通常では通れない場所を通ることが出来る。
この力の凄い所は上達すると振動が出ない。
そのため、気配を絶てば、誰にも気付かれずに、進入する事も出来るのだ。
日本で言えば忍者とかに最適な能力だ。
僕らは【ニエンテ】を使って、サウスの背後に回り込み、【伝気】でサウスの動きを止める。
「ぐ、が……な、なにした、てめえら?」
さすがは腐っても上位眷属だ。
本来ならしゃべることさえ出来ないはずなんだけどな。
【伝気】には、物を生きているように動かす事も出来れば、反対に、生きている者を動かなくする事も可能だ。
生き物という事は電気信号で動いているのだから、それを乱せば、固まって動けないというからくりだ。
僕らは質問に答える変わりに、サウスの首を跳ね飛ばした。
トドメは【錬想】で作り上げた、特別製の杭を心臓に指して、絶命させた。
実力を出さないというのなら、出さなくて結構。
相手の実力を知る必要はない。
ただ、倒させてもらえば、それで良い。
僕達は、サウスを苦もなく、撃破した。
それを見た、残る三名の上位眷属の顔が……
変わらない。
ニタニタしているだけだった。
ベネディクトは快楽主義者で、何を考えているかよく解らない男だった。
その子供である上位眷属達も性格的に似ているのかも知れない。
少なくとも、自分達と同じくくりで名前をつけられた仲間がやられたというのに全然、気にした様子はない。
「じゃあ、次はぼっきゅん、いくねぇ〜」
続いて来るのはウエストだ。
サウスが為す術無く倒れたというのに、他の二人と協力して戦おうというそぶりは見せない。
ウエストはフラフラとこっちに向かってきたと思うとどんどんぶくぶく太っていって、目の前に着く頃には五メートルくらいの背丈の巨体となった。
何処からが腹で、どこからが胸かも解らない醜い姿だった。
だけど、その姿からは考えられない程のスピードで僕らに襲いかかってきた。
超重量級のその突進力に、僕らは圧倒される。
シャーロットは冷静に剣山入りの落とし穴を作り出し、僕がそこに誘い込んで落とした。
ウエストのウエストは血まみれだった。
昔の僕なら思わず、目を背けるような惨たらしい状態だった。
それを自分達が仕掛けるようになるとは当時の僕は夢にも思わなかっただろう。
だけど、僕らはリチュオル家と戦って行かなければならない。
こんな事は余裕でやらないといけないんだ。
僕は落とし穴にはまって剣山で釘付けになって身動きが取れないウエストに追い打ちの連撃を放って、倒した。
――味気ない……全く味気ない戦いだ。
上位眷属ってのはこんなに弱いのか?
続く、ノースも全然大したことなかった。
あれだけ、警戒していたのは何だったんだろう……。
僕とシャーロットは口にこそ出さなかったけど、お互い目を合わせてそう思っていた事を確認した。
「勝ったと思った?」
残ったイーストが不気味な一言を発した。
勝ったと思った?だって?
どういう事だ。
何かあるのか?
「何が言いたいのかしら?もう貴方だけよ、残っているのは」
シャーロットが言い放つ。
僕も同意見だ。
「何故、じゃんけんをしたと思う?君達と戦う順番を決めるためかい?違うね。僕らはそんな事の為にじゃんけんをしたんじゃない」
薄気味の悪い笑みを浮かべて、イーストがそう言った。
ハッタリだ。
そうだ、そうに違いない。
僕らはそう思っていた。
――が、それを否定する言葉が、イーストの口から返ってきた。
「僕らはね、君らが来る前に話し合っていたんだよ。誰に力を移すかをね。だから、残りカスの力しかなかった三人の力は大したこと無かっただろ?」
残りカス?
「僕らはねぇ、【特別眷属】に勝ちたかったんだよ。だけど、僕らの力は【特別眷属】には遠く及ばない……だったら、四人の力を一つにまとめたらどうだろうか?そう、話あっていたんだよ」
な、なんだって?
「だから、じゃんけんは負けた順に戦う事を決めていたんじゃない。誰に力を注ぐかを決めていたんだ。残りカスになった彼らは存在自体が意味がなくなったからね。だから、それぞれが自ら死を選択した……君達に殺されるという死の選択をね」
つ、つまり、残ったイーストが本来の【上位眷属】の力を持っているって事なのか?
しかも、最低でもその4倍の力を持っていると?
それを物語るように、一斉に生物がその場から飛び立っていった。
僕らは戦慄する。
目の前の敵はそれまで、倒した三名より遙かに強いかも知れないからだ。
だけど、敵は待っちゃくれない。
イーストの背中がふくれあがり、そこから糸のようなものが四方八方に噴射される。
いわゆる蜘蛛の糸というやつだ。
蜘蛛型のモンスターと戦って来た経験からこの糸の攻略法は解っている。
糸の中心から放射状に出ている糸を縦糸と言い、円を描くような糸を横糸と言って、通常、粘り気があるのは横糸のみで、縦糸を通れば難なく、通れるというセオリーがある。
だけど、僕には解る――
これはただの糸じゃない。
どこか異質のものだ。
「道久」
「解ってる、シャーロット」
「私が中和ずるぞ」
「解った、僕が行く」
シャーロットと僕は連携して攻撃を仕掛ける事にした。
シャーロットが糸を中和して、普通の糸に変換作業を担当して、僕が、縦糸を通って網の中央に居るイーストに突っ込む。
糸が普通じゃないのは泡――あぶくのようなものが無数に糸の上を移動しているからだ。
シャーロットは既に、知覚出来ない光学迷彩分析装置を【錬想】で作り出していて、あぶくの成分を分析していた。
それを握手による骨伝導通信で敵に聞こえないように僕に情報をくれていた。
あぶくは劇物。
そして、猛毒でもある。
生き物のように糸の間を移動するあぶくに気を取られているとイースト自身への警戒が薄れる。
それを防ぐために、シャーロットは後方支援。
僕が先陣を切って戦うというスタイルを取った。
元々、戦闘能力が他の兄弟より劣るシャーロットは後方支援タイプでもある。
その力不足を補う戦力として僕が、【剣】となり、エヴァーロード家に入ったんだ。
だからこれは通常の基本スタイルと言って良い。
迎え撃つイーストが大きく息を吸い込んだ。
来る!
「シャーロット、耳だ」
僕が、叫ぶ。
コンマ数秒遅れて、糸の網を巨大スピーカーと化した超大音響が響き渡る。
ギーというまるで黒板に爪を立てたような音を大きくしたような不快な音だった。
だけど、僕とシャーロットは【錬想】で作り出した絶対防音ヘッドフォンで防御した。
危ない、後コンマ一秒遅れていたら、鼓膜が破れていたかもしれない。
つづけて背中がアルマジロの様になってくるくる回ってこっちに向かって転がってきた。
そのスピードは百メートルを4秒くらいで来るくらいだ。
かなり早い。
破壊力はダンプカーに突っ込まれた以上だ。
大きな岩の塊が四散した。
僕は【錬想】で巨大なかぎ爪を作り、それをシャーロットにパスした。
彼女は巨大なボウガンを作り、それにかぎ爪をはめて、発射する。
実はその見せかけだけ大きくしたかぎ爪には仕掛けがしてある。
イーストが防御の為に金属で出来たカニの様な皮膚に変化させたとき、かぎ爪は命中する瞬間、破裂した。
中から王水が飛びだした。
濃塩酸と濃硝酸を混合してできる橙赤色の液体である。
「ぎぃやあああああ……」
悲鳴をあげるイースト。
イースト――こいつは確かに強い。
だけど、戦闘に対してこいつはゆるみきっている。
適当過ぎる。
戦いに対して、適当にやって勝てるというのは圧倒的な戦闘能力の差があって初めて成立する。
つまり、余裕の証だ。
イーストの余裕は自身の変幻自在の攻撃方法を自慢したかったのだろうけど、僕らもそれなりに実戦経験を積んでいる。
予測以外の事態にも連携して対処出来るようになっているし、舐めてかかれる程、僕らは弱くない。
やはり、ベネディクトの眷属は絶好のカモだ。
そう思っていた。
が、それは僕らの方の驕りだった。
登場キャラクター紹介
001 倉沢 道久(くらさわ みちひさ)
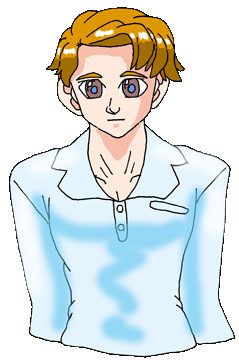
半身不随に天涯孤独となり、自ら命を絶とうとした少年。
エヴァーロード家の長女、シャーロットと知り合い、やがて、自分探しの旅に出て、成長していく事になる。
002 シャーロット・エヴァーロード
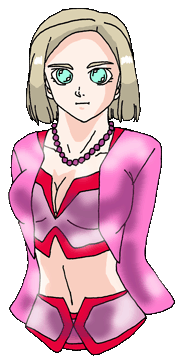
道久を自らの剣とする事で、リチュオル家との戦いに参戦しようと思っているエヴァーロード家の長女。
才能的には兄妹達の中では最弱。
そのため、参戦は認められていなかったが、パートナーを得て参戦を試みるようになる。
003 アドルフ・エヴァーロード
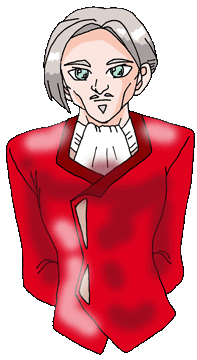
エヴァーロード家現当主で、シャーロット達の父親。
かつては力のある存在だったが、末子クレアが産まれた時、力を失う。
次の後継者としてシャーロットを選ぶが、それは戦線から離れる事を意味している。
004 アルバート・エヴァーロード
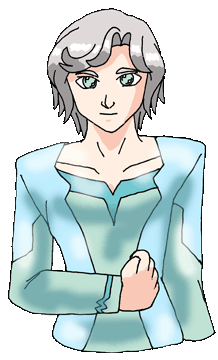
エヴァーロード家の次男でエヴァーロード家では最強と目されている青年。
心優しい性格で、シャーロット達の事も気にかけている。
天才と言われているだけあり、かなりの実力を秘めている。
005 フレデリック・エヴァーロード
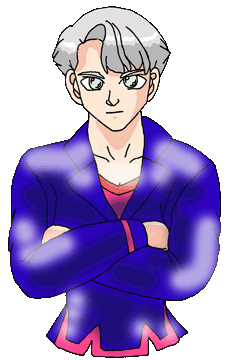
エヴァーロード家の長男で、女性の参戦には反対している。
女性は家庭を守るべきと思っている。
実力はシャーロットより遙かに上の実力を持っている。
006 リチャード・エヴァーロード
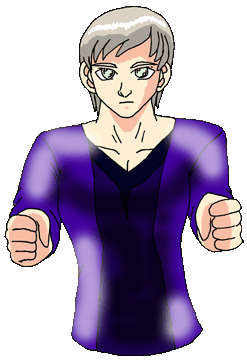
エヴァーロード家の三男で、妹のクレアに対するシスターコンプレックスを持っている。
実力的には長男フレデリックに近いものを持っている。
007 クレア・エヴァーロード
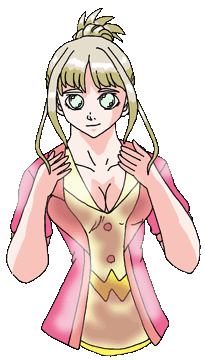
次男、アルバートに匹敵する才能を持つエヴァーロード家の次女。
最強はアルバートだが、リチュオル家が最も恐れているのはクレアだとされている。
彼女だけの技も数多く持っている才媛でもある。
008 ジュリアス・リチュオル

リチュオル家の本拠地を守る、リチュオル家最強真祖。
彼の使徒は正規軍とされている。
上位にいるのは全て女性型使徒。
009 エドワード・リチュオル
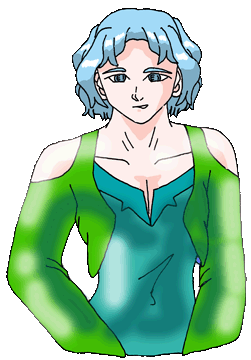
きっちりした性格の真祖。
使徒はナンバー制になっている。
統制の取れた使徒達を持つ。
010 デイヴィッド・リチュオル

自分とキャサリンの事が大好きなナルシストの真祖。
上位の使徒は全てデイヴィッドかキャサリンに似せて作っている。
キャサリンにアプローチをしている。
011 ベネディクト・リチュオル
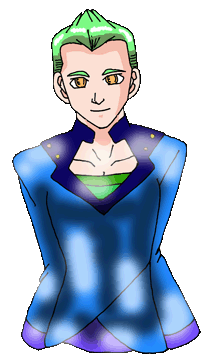
適当な性格の真祖。
自分の使徒に対して無頓着。
キャサリンにアプローチをしている。
012 セシリア・リチュオル
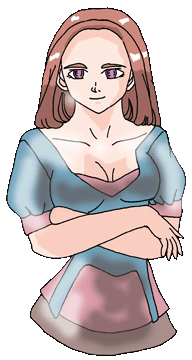
占い好きで、執念深い真祖。
特別眷属は十干と十二支の名前を使っている。
道久とシャーロットに恨みを持つ。
013 キャサリン・リチュオル
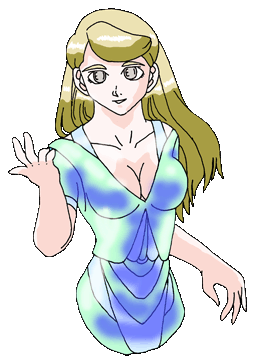
適当な性格の真祖。
その力はジュリアスに匹敵し、二強の一角を担う。
他者に対しての興味は薄い。
014 ネームレス(レス)
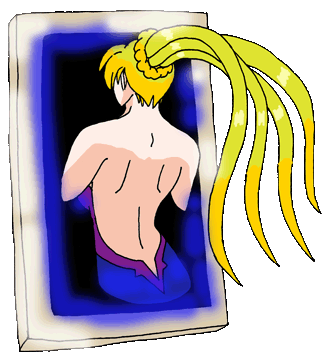
存在自体が疑われていたリチュオル家の七番目の真祖。
その力は他の6名の真祖を遙かに凌駕する。
絵画に背を向けた状態で封印されているとされている。
015 ななしのごんべい

クレアとコンビを組む事になる謎の少年。
記憶喪失になっていて、自分が誰か解らない状態。
クレアの運動能力についていくというポテンシャルを示す。