第001話
序章 出会い
「ふむ……とりあえず合格にしといてやろう。お前、名前は?」
「く、倉沢 道久(くらさわ みちひさ)です」
「そう――倉沢、光栄に思え。このシャーロット・エヴァーロードの永遠の眷属にしてやろう――さあ、舐めるがいい」
「……と言われても……」
「遠慮することはない、さぁ私(わたくし)の血を舐めろと言っている」
僕の名前は倉沢道久。
取り立てて何の取り柄もないただの学生だ。
普通の人と変わっている事をあげれば不幸ってことかな?
友達だった奴には裏切られ、家族旅行をした時に事故にあい、僕を残して家族は全員死亡、僕自身も半身麻痺の重傷を負った。
親戚らしい親戚もいないため、天涯孤独の身となった時、僕は何もかも嫌になり、世を儚んで、命を絶とうと思った。
だけど、身体が思うように動かず、死にきれず、病室の隅で泣いている時に彼女は現れた。
シャーロット・エヴァーロード……確か、僕が通っている高校に留学して来た女の子だ。
僕とは何の接点もない、本来、関わる事のない女性――のはずだったけど……
何故か病室に見舞いに来て、訳のわからない事を言ってきた。
突然、果物ナイフで自分の指を切り、その血を舐めろと言ってきたんだ。
「あの、何かご用ですか?僕はご覧の通り身体が不自由で……」
「ふむ、今はそうだな」
「今はって、これからも直る見込みなんか……」
「治るぞ、私の血を飲めばな」
「そんな訳――あの、からかうつもりなら帰って……」
「帰るつもりもからかうつもりもないぞ、私は大まじめだ。お前を私の剣として向かえに来たのだ。倉沢よ」
中二病かな?
僕はそう思った。
でも、早く帰って欲しいから、僕はとりあえず、彼女の気のすむ様に彼女の血を舐める事にした。
なのに、信じられない事が起きた。
本当に治ったんだ、僕の身体が。
殆ど動かなかった指が動く。
起き上がれなかった身体が、跳ねるように起きられた。
何が起きたんだ?
僕には状況が理解出来なかった。
「あの……僕は一体」
「ふむ、これでお前は私の物だ。これからは私の屋敷で暮らせ、良いな」
彼女は有無を言わせなかった。
ただ着いてこいと言わんばかりに僕の腕を強引に引っ張って連れていった。
世界的大富豪エヴァーロード家。
総資産は何百兆ユーロとも言われている有名な資産家だけど、その財がどのようにしてもたらされているのかは謎に包まれている。
噂では油田を日本の国土以上に持っているとか、マフィアの総元締めだとかも言われているけど、どれも違うらしい。
僕はシャーロットに連れられて、そのエヴァーロード家の当主、アドルフさんと面会する事になった。
「父上、これが私の剣です。これで私も参戦させて下さいますね」
彼女が父上と呼ぶ初老の男性はニコリともしなかった。
どうやら、彼女は何かの参加を認めてもらうために僕を連れて来たらしい。
「ならぬ、お前には荷が重い」
「何故です?リチャードやクレアですら参戦しているのですよ」
「リチャードは優秀な息子だ。そしてクレアは稀に見る天才だ。それ故に、フレデリックやアルバート同様に参戦を認めておる。じゃが、お前は別だ。お前は、戦闘には向いておらぬ」
せ、戦闘?
一体どういう意味?
「私に、子を産むためだけに生きろと、そうおっしゃるのですか?」
「そうじゃ。優秀な子を産み、次代に望みを託すのも重要な使命じゃ」
「納得、行きません、私は戦えます」
「ちょちょちょ、ちょっと待って下さい。どういう事ですか?僕は何も聞いてません」
戦闘って言われても突然過ぎて、僕に何か出来るとは思えない。
「シャーロット……話しておらぬのか?」
「この者は命を捨てるつもりでした。ならば、私がどう扱おうと勝手でございましょう」
み、見てたのか。
でもだからと言って――
「何の説明もされないまま協力する事なんて出来ません。まず、説明して下さい」
「追々、話す。今は父上と話しておる」
「シャーロット、そなたの剣とするからにはその者には聞く権利がある。話してやれ」
「で、ですが」
「シャーロット!」
「は、はい……では、聞くが良い。我がエヴァーロード家の宿年…いや、宿命を」
お父さんに言われて彼女は僕にエヴァーロード家の成り立ちと業を話してくれた。
僕自身、文才がある訳では無いのでうまく言えないけど……。
本当かどうかはわからない。だけどエヴァーロード家は元々は吸血鬼だったらしい。
吸血鬼と言えば人の血を吸って十字架とか杭とかが苦手なあれだ。
真祖でもあったエヴァーロード家は中世ではかなり人間と争っていたらしいけど、ある時、人間になる秘術を発見し、人間として生まれ変わったらしい。
その子孫が彼女達だという話だ。
人間となった彼女達は弱点もある程度、克服することも出来た。
それによって、人の世界にとけ込んで生活する事が出来たみたいだ。
人となったエヴァーロード家の役割は人間に襲いかかる怪物の魔の手から人々を守る事らしい。
そのために必要な財力を様々な国から得ているみたいだ。
巨万の富を得る代わりに命を賭けて人の脅威となる者と戦わなければならない。
それが、エヴァーロード家の宿命なのだとの事だ。
人になったとは言え、超人的な力を今も持ち続けているエヴァーロード家だから出来る事でもある。
人間の敵となる怪物は数多くいるらしいけど、その中でも最も厄介なのが、エヴァーロード家と同じ元吸血鬼、リチュオル家でこの家系も真祖の家系らしい。
でも、その家系は吸血鬼から人間に――なってはいない。
弱点の多くが露見してしまった吸血鬼から別の何かに存在にその身を変化させたみたいだ。
そして、そいつらは総じて【ネームレス】又は、【レス】と呼ばれている。
吸血鬼や狼男などの固有名詞に当てはまらなくなったという意味でそう呼ばれているようだ。
エヴァーロード家の大望はリチュオル家の殲滅。
これが、第一目的らしい。
その戦いを現在、行っているのが、当主アドルフ、長男フレデリック、次男アルバート、三男リチャード、次女クレアで、長女であるシャーロットは参加を認められていないみたいだった。
対するリチュオル家の真祖は六名いてジュリアス、エドワード、デイヴィッド、ベネディクト、セシリア、キャサリンという名前らしい。
眷属全てが全滅するらしいので、配下の怪物をちまちま倒すより、真祖を一人、倒した方が早いので、シャーロットは真祖に戦いを挑みたいらしい。
だけど、彼女の実力では配下の怪物はともかく、真祖を倒す力は無いと言われたらしい。
プライドの高い彼女はそれが我慢できなかったらしく、彼女の剣となる眷属に適した人材を世界中を転校してまわり捜したらしい。
それで見つけたのが僕らしいのだけど……
「どうだ、大変な名誉であろう?」
「名誉って言われても、僕がその剣とやらになれるとは思えないんだけど」
「何を言う。私の目に狂いはない。お前は間違いなく、私の剣となれる男だ」
「買いかぶりだよ。僕には何の力もない」
「そうだな。今は何もない、これから身につけて行くのだから」
「え?まだ、何かするの?」
「当たり前だ。このままでは、本当に何の役にも立たん。お前はこれから強くなっていくのだ」
さも当然とばかりに語るシャーロット。
駄目だ……殆ど僕にはついて行けない世界だ。
「悪いけど、僕には」
「何が不満だというんだ?お前が私のものであると同時に私もお前のものでもあるのだぞ。我が家のものは自由に使ってもらってかまわない」
「僕には何も残っちゃいないんだ」
「だから、私が出来たじゃないか。私を守る為に戦うのでは駄目なのか?」
「そんなこと、いきなり言われても」
「私はお前に会うために二十数カ国を転校してきた。二十数カ国という事は短期間でそれだけ転校を繰り返しているという事だ。それを繰り返して、ついにお前を見つけた。お前を捜すためだけに、時間を費やしてきたのだ。友人らしい友人だって、数える程しか……いや、その者達も本当に私を友と思ってくれているのかどうかも……私にはお前が全てなんだ。私にはお前しかいない……それでも、お前にとって私はどうでも良いというのか?」
「だけど、それは家の人に認めてもらうためじゃ……」
「それだけで出来るか。私にだって好みがある……って何を言わすのだ」
「それって……」
「知らん、忘れろ!とにかく、倉沢、お前は私が認めた最高のパートナーだ。文句あるか、この野郎!」
「い、いえ、ありません」
顔を真っ赤にしてそう言われると僕にはあらがう術はない。
家の中では落ちこぼれと言われているかも知れないけど、僕にとって、彼女は高嶺の花の様な存在な訳で――そんな彼女から、【好み】だと言われては嬉しいというか恥ずかしいというか。
そして、自分を必要としてくれる人間がいるというのは凄く嬉しいんだと言うことがわかった。
彼女の為に生きよう。
そう思わせるのに十分な告白だった。
そんな僕の心の変化を確信したかの様な表情で当主アドルフさんは――
「娘を――シャーロットをよろしく頼む、若者よ」
と言った。
それが、彼女を真祖への戦いの参加を認める事なのか、それとも子供を作れという意味なのかは解らない。
けど、親公認で彼女との仲を認められたということなのだろう。
彼女と共に行くという事は恐らく厳しい戦いが待っているんだと思う。
だけど、彼女が居なければ、僕は今も半身不随のまま、人生に絶望していただろう。
彼女に救ってもらった命だ。
彼女の役に立つかどうかは解らない。
でも、彼女の為に使ってみるのも悪くないかな――そう思った。
こうして、彼女と僕の戦いは始まった。
プライドが高く、ちょっぴり恥ずかしがり屋な彼女と僕に待っている敵がなんなのかは解らないけど、僕も、エヴァーロード家にお仕えする者として、恥ずかしくない力を身につけていこうと思った。
僕はまだ、エヴァーロード家の背負っている事の重要性について何も理解していなかった。
本当に何もしていなかった。
第一章 エヴァーロード家の秘術
かくして、僕はシャーロットと行動を共にする事になったんだけど。
「ねぇ、シャーロットさん」
「何だ、倉沢?」
「基本的に僕にはどんな力が備わるの?」
「そうだな、それから説明していかないとな。まず、エヴァーロード家の秘術。それが何なのか?それを説明しよう」
「秘術?そんなのあるの?」
「当たり前だ。何の力も無しに、怪物達と戦える訳がなかろう」
「それもそうだね。で、どんな力なの?」
「エヴァーロード家はその財力を活かして世界中のありとあらゆる秘術を研究しているが、現在、基本にして、最も重要視されている力が、我が家系にはある。それが、【錬想(れんそう)】だ」
「連想?」
「恐らく、字が違う。これは日本に来た時、完成させた秘術でまだ新しい力なのだが、鍛錬の錬に想像、何かを考える方の想像の想と書いて【錬想】だ」
「連想ゲームの連想じゃないんだ」
「全く違うという訳でもない。簡単に言うとイメージを力にする力の事だ」
「イメージを?」
「そうだ」
彼女が手かざすとそこにバラの花がポンポンと出現し、しばらくすると消えて無くなった。
僕は、自分の知らない世界がまだまだある事を知った。
僕は、てっきり、秘術って言うのは吸血鬼みたいな力とか魔法や超能力みたいなものだと思っていた。
でも違っていた。
力とは日々研究をされていって、そして、改変、進化を遂げていくものだという。
例えば、魔法にしたって、時代に合わせて変化していくものみたいだ。
新しく発明された物によって、それに対応した何かが求められるという事もある。
考えて見れば当然の事だ。
人間だって、時代や環境に合わせて変化していったんだ。
能力だってそのままって事はないはずだ。
エヴァーロード家も世界中の秘術を研究し、より、優れた秘術を生み出してきたみたいだ。
「凄いんだな、【錬想】か」
「私の剣であるお前もいずれ使える様になってもらう」
「出来るのかな、僕に」
「出来るのかじゃない、出来るように、使えるようになるんだ」
「う、うん、わかった」
「日本で生まれた秘術は他にもあるぞ、例えば――」
今度は彼女の指先に静電気の様なものが発生しているのが解った。
「それは電気か何か?」
「これも字が違う。気の文字はあっているが、でんが違う。でんは電車の電ではなく、伝えるの伝だ。それで【伝気(でんき)】という。簡単に言うと気を流し、物を動かすという力だ」
彼女が触れた甲冑が独りでに動き出し、ダンスを踊ってみせた後で、ガシャンという音を立てて止まった。
魔法みたいな力だとおもった。
何でも出来ちゃう感じがした。
「す、凄いよ、これ、本当にこれらが出来れば無敵じゃないか」
「甘い、例えば【錬想】にしても、これはイメージ力がものを言う。戦闘中に、細かいイメージなどなかなか出来るものじゃない。【伝気】についても同じだ。繊細なコントロールと集中力が必要となる。戦闘中に別の事を考えるのは命取りにもなりうる。最大の攻撃力であると同時に、危険性をかなり孕んだ戦い方でもある」
「な、なるほど、奥が深いね。それは」
「【錬想】については兄のアルバートと妹のクレアが優れている。故に二人は天才とされている。戦闘中に使えないのは私だけだ。どうしても集中出来ない」
【錬想】は現在におけるエヴァーロード家最大の秘術。
その為、戦闘中にこれが使えない彼女はリチュオル家への挑戦権が与えられないみたいだ。
エヴァーロード家の秘術は【錬想】と【伝気】だけではない。
だから、他の秘術を駆使してとも思うのだけど、最強とされる力を使えるのと使えないのとでは大きな戦力差があるらしい。
彼女は【剣】である僕と連携を取って、【錬想】使う事でリチュオル家に対抗しようという思惑があるみたいだった。
彼女が後衛でイメージを高め、前衛である僕が【錬想】を使うという戦法をとるつもりだ。
どうやら僕には、【錬想】を覚えてもらいたいみたいだ。
彼女は基本と言ったが僕には基本とは思えない。
この【錬想】を極めるためにエヴァーロード家の拠点を日本に置いていると聞いた。
それに【錬想】は相当高度な秘術だ。
一朝一夕に身につくようなものじゃない。
だけど、他の秘術を覚えていたら、【錬想】を覚えるのはずっと後になる。
その間、彼女は参戦出来ないという事になる。
だから、まず、【錬想】を覚えさせるつもりなんだ。
僕にはそう思えた。
そして、一刻も早く、僕を使える戦力にしたいと願う彼女との修行が始まった。
修行と言っても普通の修行とは違っていた。
まずは、イメージトレーニングだった。
彼女が【錬想】によって作り出すイメージを具現化にではなく、僕の頭に直接送り込むというものだ。
とは言え、僕は身体の基礎が出来ていなかった。
だから、身体の基礎を作り替える事も同時進行で行われた。
彼女の血を舐めているとは言え、僅かなので、僕自身には大した力はない。
それを、特別な秘術で作り出した薬を百種類以上服用し、僕の身体を作り替えていった。
それこそ、死ぬより痛い思いをし続けた。
簡単には強さは手に入らないという事だ。
その超激痛に耐えながら彼女のイメージを受け取るという修行は想像を絶するものだった。
何で僕がこんな目に――
そうも思ったけど、彼女に僕が全てだと言われた事がまるで媚薬のように僕の背中を押し、痛みに耐える気力を与えてくれた。
痛みに耐えかねて死のうと思えば死ねる。
いつでも舌をかみ切れば、窒息死することが出来る。
だけど、彼女の事を思うと、僕は死ぬ気にはなれなかった。
彼女の力になりたい――そう、思っているからだ。
僕は彼女の虜になっているみたいだった。
そして、第二の人生を与えてくれた彼女に恩返しがしたい。
この痛みの先にはそれが出来ると思うと、不思議と力が沸いてきた。
次から次へと課される試練にも僕は耐えきる事が出来た。
そして、三ヶ月――
その月日はあっという間に経ち、僕は彼女の剣として成長する事が出来た。
何とかなった力は【錬想】だけ。
だけど、この力があれば、僕は彼女の剣となれ、盾となれる。
僕と彼女は二人で一人前なのだから。
共に戦って行こうと思っている。
「見違えたな――三ヶ月前とはまるで別人だ」
アドルフさんが褒めてくれた。
彼に参戦を認めてもらおうと彼女と二人でお願いに来ていた。
「アドルフさん――僕からもお願いします。彼女の参戦を認めてあげて下さい。僕も協力します」
「それとこれとは話が別じゃ。君もシャーロットも真祖共の恐ろしさを知らぬ。我が一族で、真祖を倒した者はいまだかつて誰一人おらんのだ。フレデリック達でも勝てるかどうか解らぬのだぞ」
「父上、それは百も承知です。でも、あえて私は、私達は挑戦したいのです」
「どうしてもというのならば、実力を解らせるしかあるまい。アルバート、アルバートはおるか?」
アドルフさんが呼んだのは一族最強の呼び声も高い、次男、アルバートさんだ。
彼なら、真祖を倒せるのでは無いかという期待もされている。
シャーロットと彼とでは才能という点では天と地ほどの開きがあると言われている。
彼とまともに戦えるのは一族の中ではクレアちゃんただ一人っていう話だ。
――と言っても実際、シャーロットとアドルフさん以外には会った事ないので、メイドさん達のうわさ話でしか聞いた事ないんだけど。
「ここに居るよ、父さん」
僕らの背後から突然、声がしたのでふり向くとそこには優しそうな顔立ちの男性が立っていた。
全然、気配に気付かなかった。
いつから居たんだ?
「あ、アルバート兄さん、いつの間に?」
「やぁ、シャーロット、隙だらけってやつだね。まだまだ、修行が必要だね」
「アルバート、シャーロットが参戦したいと申しておる。どうにかならぬか?」
「僕にシャーロットの力量を計れと?」
「そうだ。お前の相手も出来ぬようでは話にならぬ」
「こりゃまた、手厳しいな」
そうだ、アルバートさんの言う通り、彼はフレデリックさんやリチャードさんでもまともに相手にする事は難しい程の腕だって、言っていた。
参戦の条件としては厳しい。
「いえ、兄さん。貴方に軽くあしらわれるようでは私が出ても犬死にでしょう。挑戦させて下さい。お願いします」
「なるほどね、君が他者に頭を下げるとはね。傲慢さが少し取れたようだね。倉沢君だっけ?彼とパートナーになったのが良かったのかも知れないね。父さん、僕からもお願いします。彼女にチャンスをあげて下さい。条件はクレアが参戦を許された時と同じで良いかい?」
「ありがとう、兄さん。かまいません。それでお願いします」
「やれやれ……クレアを許してシャーロットを許さぬ訳にもいかぬか――だが、アルバート、私情は挟むな。これは遊びではない」
「解ってるよ、父さん、なら行くよシャーロット」
「はい」
何が始まろうとしているんだ?
僕とシャーロットはアルバートさんに勝てるのだろうか?
緊張する僕らを一瞥し、彼は消えた。
「ど、どこに?」
「上だ、倉沢」
「え?あ……」
ふと、天井を見たら、アルバートさんが逆さまに立っていた。
あったはずのシャンデリアが無くなって、代わりに逆さまに灯ったろうそくが五十本近く天井にくっついている。
恐らく、アルバートさんが作り替えたのだろう。
「試験は三つ。三つとも合格点を出せたら、君の参戦を認めよう。まずは手始めにこの五十本のろうそくを一つでも吹き消せれば一つ目は合格だ。制限時間はこのろうそくが自然に消えるまでだ。良いね?」
「はい、承知しました。行くぞ、倉沢」
「あ、うん――行こう」
考えるより先に、僕とシャーロットは天井に飛んだ。
高いとは感じなかった。
また、天井は床から十メートル以上あったけど、僕の今の跳躍力ならそれは訳はなかった。
バラバラに立ててあるろうそくの火を守るのは難しいと思う。
これはアルバートさんに圧倒的に不利なのでは?
そう思ったのは間違えだった。
彼は僕らがバラバラにろうそくの火を消そうとろうそくに近づくといつの間にか接近して僕らを床にたたき落とした。
「どうしたんだい?こんなものなのか?」
「いえ、兄さん、これからです」
「そうだ、そうです」
僕らは考えつく限りの連係プレイでろうそくを狙ったが、彼は冷静に対処し、僕らを撃退していく。
考えてみれば、凄いと思う。
彼は、逆さまに立ち、かつ、ろうそくを五十本、逆さまにともして、僕らを撃退しているのだから。
分身も作り出したりもするし、イメージの具現化は本当に僕らなんかのものとはレベルが違うと言った感じだった。
何度も何度も挑戦し、その度にはたき落とされていく僕らだったけど、ろうそくが後、一センチとなった時、何とかろうそくの炎を一つ消すことが出来た。
【錬想】によって、作り出した粉塵に火花を与えて粉塵爆発させ、その風圧で一つ消したんだ。
アルバートさんは咄嗟にガードしたけど、一つだけ見落としがあったのか、それを消すことに成功した。
いや、彼の表情からすると彼のミスではなく、オマケで消させてもらったというのが正解だろう。
「次はこれだよ」
「こ、これは」
アルバートさんが作り出したのはミニチュアの立体迷路だった。
そして、同時に僕とシャーロットの身体を小さく変え、迷路の中に僕らを送り込んだ。
「制限時間は一時間。その迷路から抜け出さないと身体が元に戻り、小さな迷路の中で圧死するよ」
「望む所です。行くぞ、倉沢」
「うん」
これは彼女の得意分野だった。
実力が伴わない分、彼女は工夫をする事で、その力不足を補ってきた。
だから、頭脳戦は得意だった。
七つの超難問をいとも容易く解き、最後の関門である出口の謎もあっさりと見抜いた。
出口は外側ではなく、迷路の中心にあった。
空気の流れを利用して、見事にゴールまでたどり着いた。
見た目に惑わされないという事を試す為の試験でもあったのだ。
僕らは半分の時間の三十分足らずで迷路を突破した。
「最後だ、この四体を相手にどう戦うか見せてもらおうか」
そう叫ぶアルバートさんは四体の怪物を作り出した。
どれも見たことのない姿をしている。
どんな攻撃をするのか解らない。
僕とシャーロットは二人で一つだ。
だから連携が命でもある。
では、僕らより多い数を相手にどういった連携を見せるか?
それを見るためのテストなのだろう。
だから、僕らの倍、四体の怪物を出したのだろう。
僕らは攻撃をかわしながら、四体の怪物を観察する。
一体目はもじゃもじゃだ。
毛むくじゃらの身体に無数の棘が混じっている。
二体目は虎の身体にワシとワニ、象の首がくっついているキメラだ。
背中には蝙蝠の翼が生えていて、尾は六本だ。
三体目は肥大化した右腕に八本の左腕、首は亀のように引っ込む。
背中はアルマジロのような感じになっている。
四体目はゴーストのようだ。
無数の思念体が合わさったような感じだ。
属性などは全て不明。
見た目からはどんな能力を有しているのか全くわからない。
僕らは逃げ回りながら、能力を分析していった。
そして、【錬想】で壁をどんどん作っていった。
逃げ道はなくなるが、敵も一体ずつしか通れる幅がない。
僕らは入り口と出口でうまく、四体の怪物を挟み撃ちにした。
まずは、僕はゴーストモドキを【錬想】で作り出した網で捕獲した。
見た目はゴーストだけど、中に大きなカメムシの様な生物が入っていた。
僕はそれを見抜き、虫を捕るように捕獲した。
シャーロットも毛むくじゃらを相手にした。
彼女は自身の髪に【錬想】の力を与え、自在に動く髪の毛で毛むくじゃらの攻撃に対抗した。
毛むくじゃらの毛で縛り上げ、やはり捕獲した。
残すはキメラと九本腕の怪物だ。
僕は九本腕の怪物を僕に見せかけて、シャーロットはキメラを彼女に見せかけて、相打ちにさせた。
連携プレイで見事に四体の怪物を倒した。
「お見事!なかなかのものだったよ、お二人さん」
「アルバート兄さん……」
「アルバート、情けをかけるなと」
「父さん、シャーロットが参戦出来なかったのは戦闘において、【錬想】が出来なかったからだ。でも、彼女は立派に使いこなしていたと思うよ」
「それは、そうだが……」
「認めてやろうよ。命がけだってことは彼女も十分承知しているはず、彼女だけ、参戦出来ない理由は無いはずだよ、違うかい、父さん?」
「そうだな…確かにそうじゃ……じゃが、くれぐれも無理をするな、シャーロットよ」
「はい、ありがとうございます父上、そして、アルバート兄さん」
「真祖は僕の様に甘くないよ。それだけはくれぐれも注意してくれ。僕は君達を死なせるために参戦を認めた訳じゃないからね」
「はい。わかりました」
こうして、僕とシャーロットは真祖への挑戦権を得た。
半分はアルバートさんの情けもあったけど、半分は実力でもぎ取ったものだ。
第二章 参戦前の一時
僕らは、一月半後に、真祖を追って、旅にでる。
でも、その前に思い出を作ろうと準備が整うまで学校に通うことにした。
学校なんて、諦めていたのに、まさか、また、通えるようになるとは夢にも思っていなかった。
僕は退学扱いになっていたけど、エヴァーロード家の力で、復学する事が出来た。
復学と言っても一月半後にはまた、学校を去る事になるんだけど、それまでシャーロットとの学生生活を楽しもうと思った。
友人らしい友人は少ないと言っていたシャーロットだけど、美人で、基本的には親切な彼女と友達になりたいと思う生徒は意外に多く、すぐに人に囲まれた。
僕もシャーロットのオマケという形ではあるものの、その輪の中に入れた。
どうやら、僕の立場は彼女の恋人というよりは彼女の家の従者か何かと思われたらしい。
悲しい事だけど、入院前の僕の事を覚えている人間は見あたらなかった。
修行によって顔つきや肉付きが変わってしまっているけど、誰も覚えていないというのは少し残念だった。
あわただしいまま、一日目の復学が終わり、帰りの車の中で、僕とシャーロットは学校の楽しい事等を話した。
「ふむ、学生生活というのもなかなかに楽しいものだな」
「そうだね」
「なんだ、お前はあまり楽しそうではないな?」
「まぁね、僕の事、誰も覚えていなかったのがちょっと……」
「お前は以前と大分変わってしまったからな、覚えていろという方が難しいかもしれん。私は覚えていたぞ。それでは不満か?」
「不満っていうか……」
「では話題を変えよう。学校の話は追々、楽しい話題も増えてこよう。今は別の事でも話すか」
「じゃあ、シャーロットの家族の事、聞きたいな。僕には家族がいなくなっちゃったから、その……エヴァーロード家の人達の事、家族と思っても良いかな?」
「おぉ、かまわんぞ。そうだな――誰から聞きたい?」
「アドルフさんとアルバートさんには会ったけど、それ以外の人には会ってないからまず、その人達の事を聞きたいな」
「なるほど――家族なのに、それが何者なのか知らないというのも問題だな。よし、話してきかせよう。まずは、フレデリック兄さんからだ」
「長男の人だね」
「そうだ。彼は少々堅物でな。私やクレアの様な女の身での参戦を快く思っておらん。アルバート兄さんだったから、私達の参戦も認められたが、フレデリック兄さんだったなら有無を言わさず却下という事になっていたかも知れん」
「そうなの?」
フレデリックさんは怖そうな人なのかな?
そう、思った。
「次に、弟のリチャードだが」
「三男の人だね」
「そうだ。あやつは極度のシスコンでな、妹のクレアの事を溺愛しておる。で、いつもクレアにベッタリだ。実力的にはクレアの方が上だが、奴は奴なりに妹を守っているつもりでおる」
「へぇ……」
「もし、私の立場が、クレアと同じだったならば、倉沢、お前は暗殺されていたかも知れんぞ」
「こ、怖い事言わないでよ」
「本当の事だから仕方ない。で、妹のクレアだ」
「一番下の妹さんだね」
「あぁ、そうだ。だが、実力はアルバート兄さんに匹敵する。一族最強はアルバート兄さんだが、【レス】が最も恐れているのはこのクレアだろうな」
「なんで?」
「彼女は【セブン カラーズ オブ レクイエム】が使えるからな」
「何それ?」
「日本語に訳すと【七色の鎮魂歌】だ。【レス】の真祖六名の配下はこの歌のどれかで沈黙するからだ」
「なるほど」
「【レス】には元々、七番目の真祖がいるとされている。【レス】の名前の元になった【ネームレス】という真祖がな。その真祖の眷属がいるとすれば、それは我々の秘術の殆どが利かないとされている。利くとすれば、【錬想】か七色目の鎮魂歌だけとされている。【セブン カラーズ オブ レクイエム】はその【ネームレス】も含めた七名の真祖の属性全てに効果を与えられる」
「シャーロットはそれ使えないの?」
「私はその……音痴なのだ」
「え?今なんて?」
「二度も言わせるな。私は謳えないのだ」
「あ、ご、ごめん」
「わかれば――いい」
「失言でした」
「うむ、以上で私の家族全員だ。母は既にいない。それと、父のアドルフの事だが…私達の年齢に対し、老けているとは思わぬか?」
「そう言えば、少し――シャーロットのお父さんだったら、もう少し、若くても」
「実は、父はああ見えて四百歳なのだ」
「へぇ……四百さ……って、えー、四百歳?」
「そうだ。父は長い時を生きて来られた。一応、私は長女という事になっているが、私は百六番目の子供だ。姉に当たる人間もかつては何十人もいた」
「そうなの?」
「みんな、真祖共との戦いで散っていった」
「そんな事が」
「あったのだ。そして、そんな父もまた、百八番目のクレアを作った時、その力の大半を失った。父の代わりになる一族の人間が一人、必要になったのだ。そして、それは私がなるはずだった。だが、それを私は……親不孝かな、私は?」
「知らなかった。そんな過酷な運命をエヴァーロード家が背負っていたなんて……僕、何も知らなくて」
「いや、話してなかったのだ、知らなくとも仕方がない」
僕は、エヴァーロード家の背負っている宿命の重さを少し知った気がした。
そんなこんなで過ごして来たけど、一ヶ月半という時間はあっという間に過ぎ去った。
僕は思い残す事が無いようにシャーロットと思いつくだけの楽しい学生生活ってやつを堪能した。
新しく友達も出来、これからだという所で――
出発の時間が来た。
出発の前の日、せっかく仲良くなった友達の記憶を消して回った。
悲しかった。
これが、エヴァーロード家に与えられた業なのかと思った。
エヴァーロード家と関わると不幸になるかも知れない。
だったら、何も知らない他人でいる方が安全だからだ。
シャーロットが前に悲しい顔で言っていた友達だと思っていないかも知れないと言うのはこの事だったのかもしれない。
登場キャラクター紹介
001 倉沢 道久(くらさわ みちひさ)
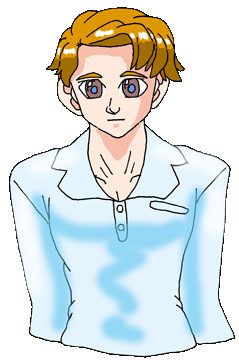
半身不随に天涯孤独となり、自ら命を絶とうとした少年。
エヴァーロード家の長女、シャーロットと知り合い、やがて、自分探しの旅に出て、成長していく事になる。
002 シャーロット・エヴァーロード
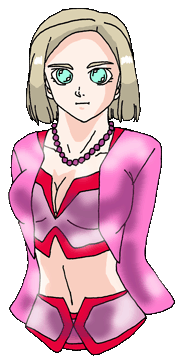
道久を自らの剣とする事で、リチュオル家との戦いに参戦しようと思っているエヴァーロード家の長女。
才能的には兄妹達の中では最弱。
そのため、参戦は認められていなかったが、パートナーを得て参戦を試みるようになる。
003 アドルフ・エヴァーロード
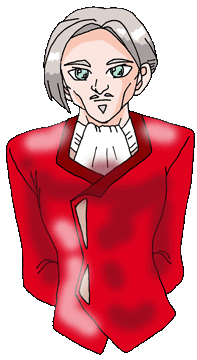
エヴァーロード家現当主で、シャーロット達の父親。
かつては力のある存在だったが、末子クレアが産まれた時、力を失う。
次の後継者としてシャーロットを選ぶが、それは戦線から離れる事を意味している。
004 アルバート・エヴァーロード
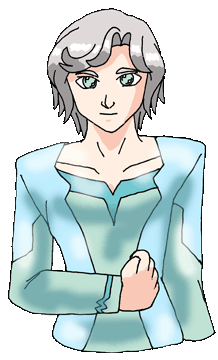
エヴァーロード家の次男でエヴァーロード家では最強と目されている青年。
心優しい性格で、シャーロット達の事も気にかけている。
天才と言われているだけあり、かなりの実力を秘めている。
005 フレデリック・エヴァーロード
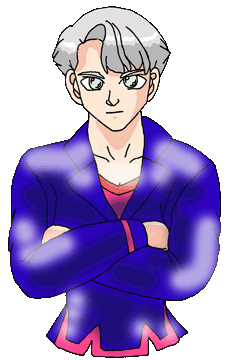
エヴァーロード家の長男で、女性の参戦には反対している。
女性は家庭を守るべきと思っている。
実力はシャーロットより遙かに上の実力を持っている。
006 リチャード・エヴァーロード
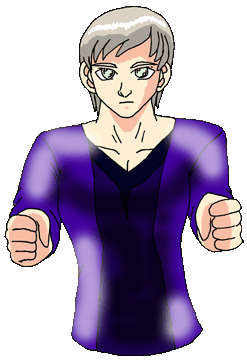
エヴァーロード家の三男で、妹のクレアに対するシスターコンプレックスを持っている。
実力的には長男フレデリックに近いものを持っている。
007 クレア・エヴァーロード
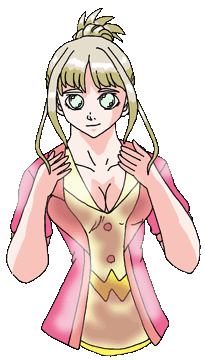
次男、アルバートに匹敵する才能を持つエヴァーロード家の次女。
最強はアルバートだが、リチュオル家が最も恐れているのはクレアだとされている。
彼女だけの技も数多く持っている才媛でもある。
008 ジュリアス・リチュオル

リチュオル家の本拠地を守る、リチュオル家最強真祖。
彼の使徒は正規軍とされている。
上位にいるのは全て女性型使徒。
009 エドワード・リチュオル
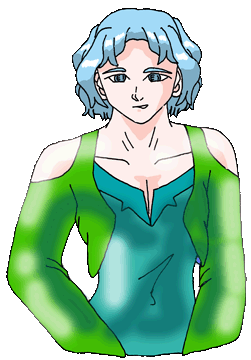
きっちりした性格の真祖。
使徒はナンバー制になっている。
統制の取れた使徒達を持つ。
010 デイヴィッド・リチュオル

自分とキャサリンの事が大好きなナルシストの真祖。
上位の使徒は全てデイヴィッドかキャサリンに似せて作っている。
キャサリンにアプローチをしている。
011 ベネディクト・リチュオル
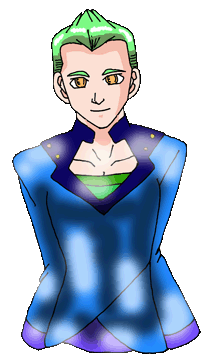
適当な性格の真祖。
自分の使徒に対して無頓着。
キャサリンにアプローチをしている。
012 セシリア・リチュオル
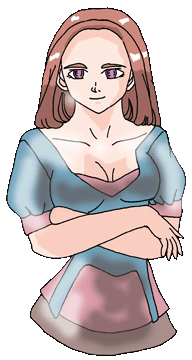
占い好きで、執念深い真祖。
特別眷属は十干と十二支の名前を使っている。
道久とシャーロットに恨みを持つ。
013 キャサリン・リチュオル
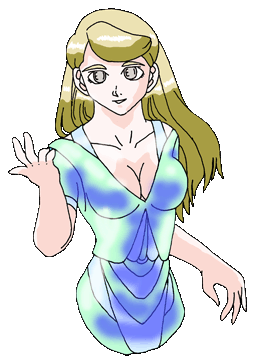
適当な性格の真祖。
その力はジュリアスに匹敵し、二強の一角を担う。
他者に対しての興味は薄い。
014 ネームレス(レス)
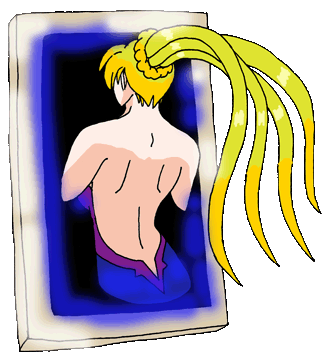
存在自体が疑われていたリチュオル家の七番目の真祖。
その力は他の6名の真祖を遙かに凌駕する。
絵画に背を向けた状態で封印されているとされている。
015 ななしのごんべい

クレアとコンビを組む事になる謎の少年。
記憶喪失になっていて、自分が誰か解らない状態。
クレアの運動能力についていくというポテンシャルを示す。